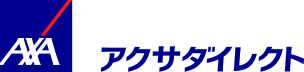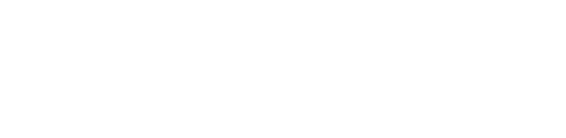法人向け自動車保険
法人向け自動車保険お役立ち情報
車を会社名義にするメリットとは?
契約・変更手続き方法と注意点を解説
更新日:2025年1月21日
公開日:2024年7月31日
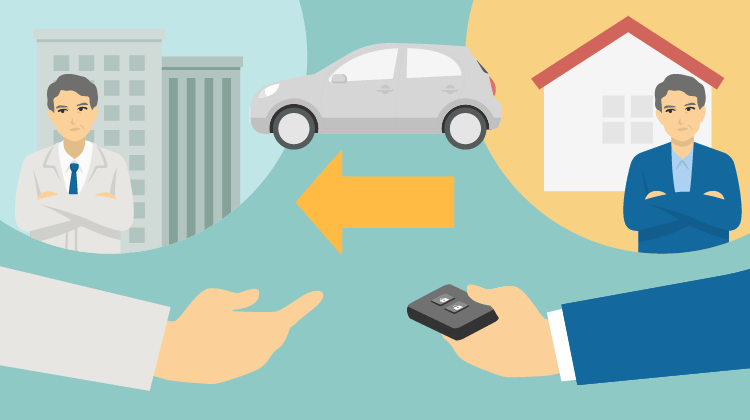
仕事で車を使う場合、経営者の方は会社名義(法人名義)での車の購入や名義変更を検討されることが多いでしょう。会社の経費として処理できる項目が増えることで節税が見込まれる一方、手続きや私的利用のリスクに関しては正しい情報が必要です。車を会社名義とした場合のメリットや注意しておきたいポイント、名義変更手続きや私的利用の取り扱いについて解説します。
車を会社名義にした方が良いといわれている理由は?
会社を経営している方の中には、自家用車を仕事でも使用するケースが見られます。その場合、車は個人名義よりも会社名義(法人名義)にすることで、節税やローンの組みやすさにつながると考えられます。
代表者個人の可処分所得を増やすことができる
個人名義の車を会社名義にすると、車に関連する費用を会社の代表者個人が家計から支払う必要がなくなるため、個人の可処分所得(*)が増えます。個人名義の車の場合、その購入や維持にかかる費用は所有者が負担しなければなりませんが、会社名義であれば、車に関連する費用は会社の経費として計上できるからです。
可処分所得とは、税金や社会保険料を控除した後の自由に使えるお金(手取り収入)のことです。
法人税の節税につながる
法人税は事業で得た所得に対して課せられる税金で、益金(売上など)から損金(経費など)を引いた金額(課税所得)をベースに算出します。会社名義の車を所有することで経費が増えると課税所得が小さくなるため、結果として法人税額も下がり、節税につながります。
会社名義の車の場合、車の購入費用や税金、自動車保険料、ガソリン代、駐車場代、車検代などが経費として認められます。新たに車を購入した際の費用は減価償却費として計上することができ、大きな割合を占めるのがポイントです。なお、節税できるのは会社として納付すべき法人税であって、個人の所得税や住民税の節税につながるわけではありません。
節税の詳しい仕組みについては、なぜ自動車を買うと節税対策になるのか?税金が安くなる仕組みと理由を解説!をご覧ください。
法人名義でローンを利用できる可能性がある
会社名義の車も法人の信用力や支払い能力に関する審査に通れば、ローン購入が可能です。まとまった初期費用を準備するのが難しい場合や、手元に資金を残しておきたい場合に有効でしょう。
個人名義で車をローン購入する場合、貸金業法の「総量規制」の影響を受けることがあります。総量規制とは、個人の借入上限を年収の3分の1までに制限する仕組みのことです。マイカーローンは総量規制の対象外ですが、そのほかの借入があると審査で不利に働く場合があります。
一方、法人名義の場合は、会社としての信用力がしっかりしていれば、代表者個人の信用力が不十分な場合でも、法人向けローンを利用できる可能性があります。
仕事用の車を会社名義にした場合に経費にできる費用
会社名義(法人名義)で車を所有する大きなメリットの1つが、購入費以外の関連費用も経費として計上できる点です。個人名義のままでは経費にしづらかったコストも、法人として所有することで会社の利益から差し引けるようになり、節税効果が期待できます。では、具体的にどのような項目が経費に含められるのでしょうか。
車に関連する税金
会社名義の車の場合、関連する各種税金を経費として計上できるようになります。車にかかる主な税金は、次の4つです。
自動車税/軽自動車税
毎年4月1日時点での車の所有者に課せられる税金です。車の種類(普通自動車・軽自動車)や排気量によって金額が異なります。
自動車重量税
車の新規登録時や車検時に支払う税金です。車両の重量に応じて課せられるため、車両が重いほど金額も大きくなります。
環境性能割
車両の燃費や排気ガス性能にもとづき、新車購入時に課せられる税金です。環境性能が高いほど税率が低くなります。
消費税
車両本体の価格やメンテナンス費用など、車の購入・維持にかかる費用に付随して発生する税金です。会社名義で購入した場合、支払った消費税は仕入税額控除の対象となります。
上記のほか、法人の場合は、車両の種類によって固定資産税がかかるケースもあります。
自動車保険料
自動車保険には、法律で加入が義務づけられている「自賠責保険」と、任意で加入する「自動車保険(任意保険)」の2種類があり、いずれの保険料も経費計上が可能です。ただし、経費としての取り扱いは次のように異なります。
自賠責保険(強制保険)
1年以上の期間で契約し、保険料を一括で支払った場合でも、加入した年度に全額を経費計上できます。
自動車保険(任意保険)
複数年分の保険料を前払いした場合でも、1年分の保険料を年度ごとに計上します。
そのほかの維持・管理費
税金や保険料以外にも、車の日常的な維持や管理にかかる費用も経費として計上可能です。たとえば、ガソリン代や整備・修理費、洗車代、駐車場代、車検費用などが該当します。車の使用頻度が多い場合や、保有台数が多い場合は、維持・管理にかかるコストも大きくなるため、経費計上できることもメリットといえるでしょう。
会社名義で車を購入する流れ
以下のような3つのステップで購入します。
1. 事業に合った適切な車種を選ぶ
車種や乗車可能人数を絞り込みます。会社名義である以上、業務においてどのように利用するのかを明確にしておきましょう。
2. どこで買うかを決める
車をどこで買うかも重要です。例えば、ディーラーで車を購入すると、利用中や売却時のサポートを受けられるなどのメリットがあります。法人の場合は、事業ニーズを理解してくれるところを選ぶと安心でしょう。
3. 必要書類をそろえる
どの車をどこで購入するかが決まったら、契約に必要な書類を用意します。車の種類やローンの有無によって準備する書類は異なるので、事前によく確認しましょう。
会社名義で車を購入する場合の注意点
会社名義(法人名義)で車を購入する際は、いくつか注意点があります。購入タイミングや耐用年数、カーリースの検討といったポイントが考えられるため、確認しておきましょう。
購入するタイミング
会社名義で車を購入する場合、そのタイミングは事業年度の初月をおすすめします。そうすることで、初年度に1年分の減価償却費を計上できるからです。車の購入費用は減価償却という方法によって、数年に分けて経費にします。この減価償却は1ヵ月単位で計算するというルールがあります。
例えば、3月決算の会社が3月に車を購入しても、その年の減価償却費は1ヵ月分しか計上できません。一方、4月に購入して使用を開始すれば減価償却費は1年分となるため、より大きな金額を経費とすることが可能です。特に、一括購入した場合は初年度の支出金額が大きくなるので、減価償却の仕組みをよく理解して、最大限の経費計上ができるようにしておくとよいでしょう。
購入する車の耐用年数
節税の要となる減価償却費は、耐用年数が大きく影響します。耐用年数とは、車を通常どおりに利用できるとされる期間のことで、この期間に応じて経費が計上されます。新車の場合、普通車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年と定められているので、新車の普通車を600万円で購入した場合は600万円を6年に分けて経費計上します。
なお、中古車の耐用年数は普通車・軽自動車に関わらず、新車の耐用年数のうち何年経過しているかによって変わります。
条件によっては1年で償却できるケースもある
仕事用として「中古車」を購入する場合、残存する耐用年数によっては、1年で全額を償却できる場合があります。中古車は新規登録から経過している年数分、耐用年数が減少しているため、耐用年数は新車とは異なり、法定耐用年数にもとづいて算出する「残存年数」で計算します。具体的な計算方法は、次のとおりです。
新車の耐用年数 - 経過年数 +(経過年数 × 20%)
1年未満の端数がある場合は切り捨て、2年未満の場合は2年とする。
たとえば、経過年数が4年6ヵ月 の普通車の場合、耐用年数は次のようになります。
耐用年数 =(6年-4.5年)+(4.5年 × 20%)= 2.4年
1年未満の端数は切り捨てるため、耐用年数は2年となります。この場合、定率法による償却率は「1.000」のため、取得価額の全額がその年の経費となり、1年で償却可能です。ただし、償却費は月割りで計上する必要があるため、会計年度をまたぐ場合は翌年にわたって残額を計上することになります。
仮に、会計年度が4月~翌年3月である会社が8月に該当する中古車を購入したのであれば、初年度は8月~3月の8ヵ月分を償却費として計上し、残りの4ヵ月分は翌年度に計上します。
カーリースとの比較検討
事業で使用する車は、購入以外にもカーリースという選択肢があります。カーリースとは、月額の利用料(リース料)を支払うことで車を借りられるサービスです。車の所有者はリース会社、使用者は会社となるため、車が会社の資産となるわけではありません。
カーリースは車を購入する場合のように、一括で多額の費用を支払う必要がなく、初期費用をおさえられることがメリットです。車種やグレード、カラーなども自由に選ぶことができ、経費処理も毎月のリース料を経費に計上するだけで済みます。
ただし、契約期間の途中での解約や契約内容の変更ができません。月間走行距離にも上限が定められ、事故などで車両価値を下げた場合は違約金が発生することもあります。支払い総額で比較すると購入の方が安くなる可能性もあるため、両者をよく比較検討して決めるとよいでしょう。
代表者個人や家族名義の車を会社名義に変更することはできる?
個人名義の車や家族名義の車は会社名義(法人名義)に変更できます。たとえば、個人事業主や家族経営の場合、法人化(法人成り)する際に車を会社名義に変更することがあります。厳密には、個人から会社への売却や現物出資をする、という扱いになります。また、会社名義の車を個人名義に変更することもできます。そのため、会社名義の車は減価償却が終わって購入費用を経費計上できなくなったタイミングで、代表者個人へ売却するケースも見られます。
車の名義変更を行う手順
個人名義の車を会社名義(法人名義)に変更する際は、以下の手続きが必要です。
1. 株主総会の承認
車の名義を個人から法人へ変更(売却)するには、その取り引きが株主総会で承認されなければなりません。1人会社であっても、承認の事実が明記された株主総会議事録が必要です。
2. 必要書類を準備する
名義変更には、個人・法人の双方が用意すべき書類が複数あるため、名義変更の日までに準備します。
3. 駐車場を確保し、管轄の警察署で車庫証明書を取得する
名義変更の手続きをする前に、法人名義となる車の駐車場を確保し、その場所を管轄する警察署で車庫証明書を取得する必要があります。車庫証明書は必要書類の1つでもあるので、早めに準備を始めましょう。
4. 管轄の運輸支局で名義変更する
名義変更の手続きは、会社の住所を管轄する運輸支局に申請して行います。名義変更によって管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更手続きも必要です。
法人・個人間で車の名義変更する場合の注意点
個人と法人の間で車の名義変更をする際は変更タイミングや費用面についての注意点を紹介します。
名義変更するタイミング
個人から法人への名義変更は法人の設立時でも設立後でも可能ですが、これから法人化する場合はそのタイミングに合わせるケースが多いでしょう。できる限り早めに法人名義にすることで、 経費として計上できる金額が大きくなるからです。一方、法人から個人への名義変更の場合は、原則として減価償却が済んでから行います。減価償却ができるうちに個人へ売却してしまうと、それ以降は購入費用を法人の経費とすることができなくなります。
名義変更する車の売買価格
個人から法人、または法人から個人への名義変更は、その売買価格を適正に設定しなければなりません。「個人」と「会社」は利益相反関係にあり、利益相反取引は原則禁止とされています。利益相反関係とは、一方の利益が他方の不利益になる関係を指します。
例えば、代表者個人が会社へ車を売却する場合、不当に高額な売価を設定すると会社にとっては損害となり、公正な取り引きとはいえません。名義変更に株主総会での承認が必要なのは、こうした不公正な取り引きの横行を防ぐためです。売買価格は時価(一般に取り引きされる価格)とし、個人・法人の双方が損をしないように設定しましょう。価格判断としては、数社による査定結果などを根拠資料に平均値を採用する方法などがあります。
名義変更する車の耐用年数
名義変更によって手に入れた車の耐用年数は、中古車を購入したものとして計算します。例えば、個人名義で新車の普通車を購入し3年10ヵ月乗った後、法人名義にした場合、法人名義の耐用年数は以下のとおり2年です。
例)耐用年数=(6年 - 3年10ヵ月)+(3年10ヵ月 × 20%)
=35.2ヵ月(=2.9333年)
2.9333年のうち1年未満の端数は切り捨て。
会社名義の車を売却して利益が発生すると税金がかかる
会社名義の車を個人へ名義変更(売却)して利益が出ると、法人税と消費税がかかります。「利益が出る」とは、帳簿価額よりも高く売れることです。例えば、600万円で購入した車が数年の減価償却によって、帳簿上150万円になっていたとします。この車が時価180万円での売却となった場合、帳簿価額との差額の30万円は会社の利益(固定資産売却益)として、課税対象となる仕組みです。
社用車の購入・名義変更手続きに必要な書類は?
会社名義(法人名義)での車の購入や名義変更の際は、さまざまな書類が必要です。具体的にどんな書類が求められるのかを理解した上で、準備を進めるようにしましょう。
車の新規購入時に必要な書類
会社名義で車を購入する際は、契約時に以下の書類が必要となるのが一般的です。
【普通車の場合】
- 代表者の実印または認印
- 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 車庫証明書(発行後約1ヵ月以内のもの)
【軽自動車の場合】
- 代表者の実印または署名
- 商業登記簿謄本(または抄本)、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか1つ
なお、ローン購入の場合は、銀行口座情報や届出印なども必要です。
車の名義変更に必要な書類
個人・法人間で車の名義変更をする際は、以下のような書類が必要です。
- 株主総会議事録
-
車の名義変更が承認されたことを証明する書類。
- 実印
-
個人の実印、法人の代表社員それぞれが必要。
- 印鑑証明書
-
個人・法人それぞれの証明書が必要。
- 譲渡証明書
-
旧所有者から新所有者への車の譲渡を証明する書類。
- 自動車検査証
-
車が保安基準に適合していることを証明する書類。旧所有者が用意する。
- 車庫証明書
-
車の保管場所が確保できていることを証明する書類。新所有者が用意する。
- 自賠責保険証明書
-
自賠責保険への加入を証明する書類。自賠責保険の名義変更が必要。
- 自動車税納税証明書
-
自動車税の納税を証明する書類。新所有者が陸運支局で手続きする。
- リサイクル券
-
車の解体処理費用の預託を証明する書類。旧所有者から新所有者に譲渡。リサイクル券の名義変更は不要。
- 申請書
-
車の名義変更を申請する際に記入する書類。新所有者が陸運支局で揃える。
- 手数料納付書
-
名義変更の手続きにかかる手数料を納めるための書類。新所有者が陸運支局で揃える。
- 自動車税・自動車取得税申告書
-
名義変更時に必要となる税金に関する書類。新所有者が陸運支局で揃える。
車の購入・名義変更時にあわせて行うべき手続きは?
車の購入や名義変更では車自体の手続き以外にもすべきことがあるため、ローンや自動車保険など、車の購入・名義変更に付随する手続きについて紹介します。
車の新規購入時に必要な書類
会社名義の車をローン購入する際は、車の選定とともにローンの審査と手続きも必要となります。法人向けのカーローンはディーラーや金融機関が扱っているため、事前に相談するとよいでしょう。
なお、ローン返済中はローン会社や金融機関が車の所有者となるため、「所有者」の名義変更は原則としてできません。一方、「使用者」の名義はローン会社への相談によってできる場合があります。変更したい名義が所有者である場合は、ローンを完済した後に手続きするようにしましょう。
法人用自動車保険に関する手続き
自賠責保険と自動車保険それぞれの名義を変更するのも忘れないようにしましょう。自賠責保険は車の売買契約書類などを添えて、契約者変更の申請を行います。任意加入の自動車保険の場合、個人向けと法人向けで保険商品そのものが異なるため、新規で契約することが一般的です。ただし、所定の条件を満たしていると名義変更が可能な場合もあるため、保険会社に確認してください。所定の条件に当てはまらない場合は、新規で契約する必要があるので、保険会社に確認の上で手続きを進めましょう。
会社名義の車の取り扱いに関する注意点
会社名義の車の取り扱いについて、私的利用のリスクを含め解説します。
私的利用は原則できない
会社名義の車は業務で使用されることが前提であり、私的な利用は原則として認められていません。社用車の私用に関する法律上の規制や罰則はありませんが、会社の就業規則や管理規程によって禁止されている場合があります。
もし私的に利用した場合、車に関連する費用が経費として認められず、税務上問題となる可能性があります。ただし、会社の役員などが通勤時に使用することは私的利用には該当しないとされ、業務上必要な範囲と見なされます。
トラブルを防ぐためにはルールが必要
社用車の私的利用にはリスクが伴いますが、やむを得ない事情によりプライベートで利用するケースがあるかもしれません。私的利用での事故や故障が発生した場合に備え、トラブル時の責任やコスト負担(ガソリン代や高速料金など)に関するルールを就業規則や管理規程で定めて、従業員に周知徹底することが重要です。
私的利用を認めない場合は、その旨を就業規則などで定めておく必要があります。
まとめ
日常的に業務に使用している個人名義の車を会社名義(法人名義)に変更し、経費計上することで、個人の可処分所得の増加や法人税の節税効果が期待できます。一方で、私的利用に関しては原則として認められない点には注意が必要です。また、会社名義とする車は必要書類や契約までの流れが個人名義とは異なるため、車の購入や名義変更の際は、タイミングや耐用年数などと併せてポイントをよく確認の上、手続きを進めるとよいでしょう。
監修者 佐藤 寿美礼
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP(日本FP協会認定)

監修者 佐藤 寿美礼
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP(日本FP協会認定)
2016年からフリーランスとして活動。金融や投資、税金、保険、住宅ローン、不動産、社会保障制度など、「お金」関係の記事を中心に編集や執筆をしています。子どもの大学進学やマイホーム購入などをきっかけに、お金の管理に興味を持ち、投資や保険、法律などを勉強中です。