

脳炎とは、脳の組織に炎症がおき、神経症状(けいれん発作、視力障害、麻痺など)が主な症状として現れる病気です。
原因によって感染性脳炎と非感染性のものに分けられます。感染性脳炎は病原体が脳に入り込んで悪さをするタイプで、ウイルス(狂犬病、ジステンパーなど)、細菌、真菌(クリプトコッカスなど)、原虫(トキソプラズマ、ネオスポラなど)、寄生虫(線虫類)などの感染が原因として挙げられます。
犬の場合は、このような病原体が原因ではない非感染性の脳炎が多く、脳に炎症によるしこり(肉芽腫)ができるタイプ(肉芽腫性髄膜脳脊髄炎)や、脳の実質に炎症や壊死が起こるタイプ(壊死性髄膜脳炎、壊死性白質脳炎)などがあります。原因は不明な部分が多いですが、壊死性髄膜脳炎では脳の一部の細胞に対して自分自身が攻撃をしてしまう異常(自己抗体産生)が確認されており、そのほかの脳炎も病理検査の所見や免疫抑制剤を使った治療への反応を考慮すると、自己免疫の異常による病気(自己免疫疾患)である可能性が疑われています。
感染性の脳炎か非感染性の脳炎かによって治療も大きく変わるため、犬種や年齢、症状の現れ方や神経学的検査と共に、可能であれば全身麻酔下でMRI検査や脳脊髄液検査を行い、治療方針を立てていくと良いでしょう。
症状は、脳炎の部位や大きさによってさまざまです。進行する脳炎は、神経の興奮からやがて麻痺に移行します。一般的な脳炎の症状は、けいれん発作を起こしたり、不安定な歩様、ふるえが見られたり、頭が傾いたり、同じ方向にクルクルと回ったりします。意識障害で突然かみついたり、単調に吠えたりする場合もあります。次第に食べ物や水を飲み込めなくなったり(嚥下困難)、視力が低下し盲目になり、最終的に昏睡状態になります。
感染性の脳炎やけいれん発作を何度も起こす犬では、発熱もみられます。脳炎が広範囲に及ぶ場合や呼吸を管理する神経が侵されると、けいれん発作を短時間に繰り返し、呼吸困難などを起こして死亡します。
感染性脳炎はどの犬、年齢にも起こる可能性があります。非感染性の脳炎は好発犬種として、パグ、チワワ、パピヨン、ヨークシャー・テリア、ポメラニアン、マルチーズ、ペキニーズ、シー・ズー、ミニチュア・ダックス、ボストン・テリアなどの小型犬が挙げられます。また、比較的若い犬で見られることが多い病気です。
「非感染性」の脳炎には決定的な予防法はありませんが、「感染性」の脳炎には、ウイルスに対しては予防接種がありますし、病原体が脳に達する前に治療をすることで脳炎を予防できます。普段から犬のストレスを減らし、健康的な生活をすることで免疫力を養っておくのも立派な予防法です。
感染性脳炎に対しての治療は病原体に対しての治療が主体になりますが、いずれの原因によるものでも感染症の末期の状態であり、後遺症が残ったり、死亡する場合が多いです。病原体に対しての特効薬がない場合は、対症療法が主体になり、非感染性脳炎と近い治療が行われます。
非感染性脳炎に対して確立された治療法は現在ありませんが、一般的に免疫抑制を目的としたステロイド剤など免疫抑制剤の投与、けいれん発作に対して抗てんかん薬の投与などが行われます。補助的に脳圧を下げる薬を投与したり、発作による発熱がある場合は体温調整が行われます。重症化した犬は誤嚥性肺炎を起こしやすく、その場合はそちらの治療も行われます。
感染性、非感染性に限らず致死的な経過をたどる場合も多く、治療に反応が乏しく回復の見込みがなく、苦痛を伴う状態の場合、残念ながら安楽死を選択する場合もあります。
白神 久輝 先生
埼玉県草加市にある「ぐぅ動物病院」の院長。2005年4月の開院以来、大学病院や専門病院と連携をとりながら、常に最先端の技術や機器を導入しており、飼い主の方にもわかりやすい説明でサービスを提供し続けている。また病気になりにくい体づくり(予防、日常ケア)のアドバイスも積極的に行っており、地域のかかりつけ医・中核病院として親しまれている。
※「病気事典」には「アクサダイレクトのペット保険」の補償対象外の病気や治療内容も掲載されていることがあります。









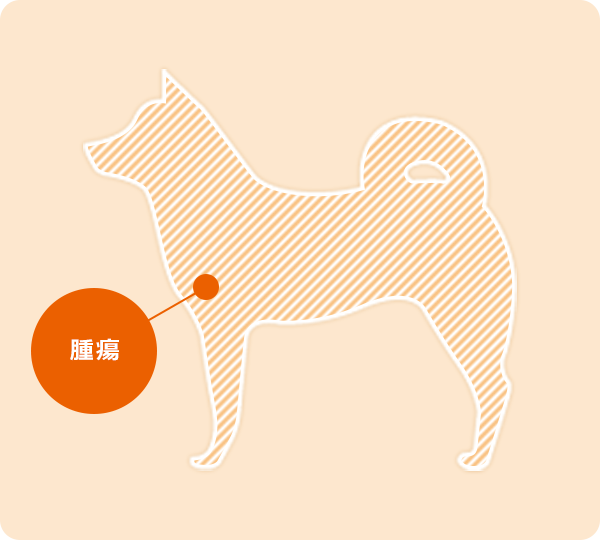

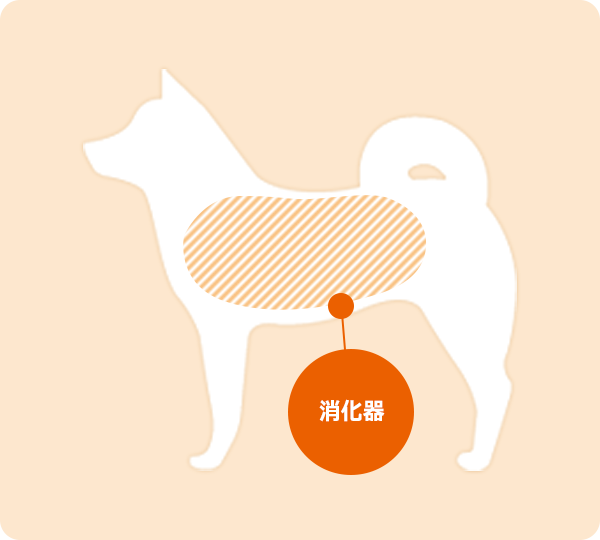



※「病気事典」には「アクサダイレクトのペット保険」の補償対象外の病気も掲載されていることがあります。
補償対象外の病気については、「契約申込のご案内(兼重要事項説明書)」をご確認ください。
よくあるご質問をQ&Aとしてまとめておりますので、お問合せの前にご覧ください